





























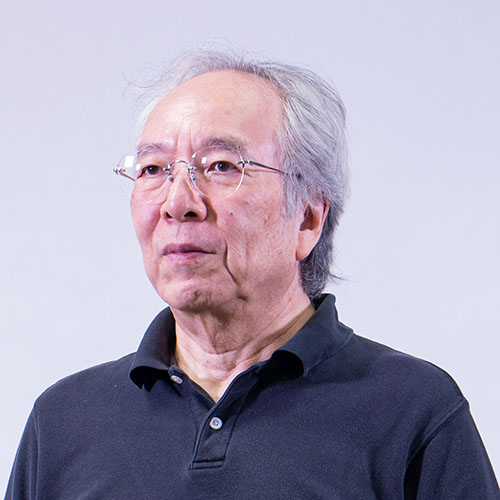
1951年生まれ。武蔵野美術大学建築学科卒業。在学中よりライターとして音楽評論や FM 音楽番組構成などを行う。81年から、当時ベンチャーであったアスキー社のニューヨーク駐在員としてメディアビジネスを調査。帰国後、雑誌創刊、情報サービス企画を担当。93 年退社し、情報関連分野のコンサルタントとして活動。
「学内で最も若い学科の一つ」と言われてきたデザイン情報学科も、今年(2009年)で設立10周年を迎えた。いまだに「どのような学科なのか、よく分からない」と言われる一方で「やっていることはバラバラだけれど、これまでの学科にないエネルギーを感じる」という声も聞かれるようになった。
確かに先行する他学科と比べると、学科名称から教育内容を想像するのは難しい。10年前、情報技術に対する社会の期待が異常に高まるなかで、本来なら拠り所となる「デザイン情報学(Design Informatics)」の定義を的確におさえることができず、また何をめざし、どのような学科とするかについて曖昧なままスタートをきってしまった。その後の何年かで過度な情報技術への期待は沈静化するのだが、積み残したこれらの問題点を明らかにする努力を怠ったことが、学科への理解が得にくい原因の一つなのではないかと思う。
しかし、日々の学科運営のなかで様々な試みを行いながら、学生たちと一緒にデザイン情報学の対象領域や学科としての方向性を明らかにしようと試み、環境整備に取り組んできたことが、なんとなくカタチになりつつあるようにも思う。あえて定義や目標を厳密に規定しないままスタートしたことが、かえって未知の可能性へと眼を向けさせ、大学でデザインを教えるということを根本から考えるきっかけともなったのではないか、とも考えている。
学科設立当初は確かな手がかりがつかめなかったが、ここ数年の経験から私はデザイン情報学を、「統合の術としてのデザイン」と「分節する知としての情報学」の掛け算、と説明するようになった。これは「全体は部分の総和より大きい」という考え方を展開したものである。簡単に言えば、「全体」をどうやって大きなものにするかは「統合」の問題である。それと同時に統合に向けて、どのような「部分」を(世界からどのように切り取って)持ちよるかは「分節」の問題である。
デザイン情報学は、すでに記号として存在する情報を取りまとめ、機能的全体を形づくる方法としての「情報デザイン(Information Design)」的な関心を一部に含んではいる。だが、もう一つの重心は世界に目を向け、そこから何を、いかに切り出すかというところにある。この考え方は、工学系というよりは芸術系のアプローチに近い。これが美術大学のなかにデザイン情報学科がある理由の一つである、と私は考える。
大学は教育機関の一つとして、過去から引き継いだ知を将来につないでいくという使命を担っている。しかしそれと同時に、新たな知を生み出す「場」としても期待されている。
大学という場は、企業のような予め決められた目標を効率よく達成するための組織とは根本的に異なる、と言われることがある。とりわけ「美の創造」を掲げる美術大学には、高校までの「教える/教えられる」といった役割の明確な知識移植型教育とは違った関係がある。入学以前にはもっぱら教師から知識を授けられる立場にいた生徒も、ここでは与えられる立場に甘んじることなく、学生として自発的に環境に働きかけるよう促される。学生の多くはおそらく初めて、新たな価値を作り出すこととそれを認められることを体験することになる。規模は小さいけれど、美大という場は、様々な立場の人々が集まって、型にはまらない交流を通じて新たな価値を作り出そうとする、文化的な枠組みだと言っても良いだろう。
このような場にあって、新設学科に何ができるのか。私たちはそれを考えながらほぼ4年単位で学科カリキュラムの再検討を行ってきた。その規準としたのは、「何が、何のために、どのように行われているのか」という具体的な視点からデザイン系学科の働きを明らかにすることだった。

上図「Heuristic Circuit(自己発見的な回路)」は、こうしたことを踏まえて、大学という場においてそれぞれの学生が行うべき試行錯誤を行為の連鎖としてまとめてみたものである。
一番内側にあるのは、作ってカタチにしたものを見て気づき、そこで考えて新たに計画し、さらに作る、というループである。何度もこうしたプロセスをくり返し、習慣化することによって学生は次第に考えをカタチにする技能を身につけていく。一方ではよく考えるために、過去から私たちが引き継いだ知や私たちが生きる時代を「読む」力、つまり広い意味での教養が求められる。さらに、作ったモノをいかに「見せる」かにも気を配りたいし、それを見たり体験した人と「話す」ことによって、自らのなかに他者の視点を取り込んでいかなければならない。これらはすべて、カタチと他人の目を通じて「気づく」ことにつながっている。
学生はこうした節目を経験として刻み込み、内省を繰り返すことでより高いレベルへ移行していくが、これらの連鎖の中心にあるのが「プラン(中間ドキュメント)」である。
デザイナーがモノやコトをカタチにしようとするとき、何の準備もなく作業に取りかかることはまずない。少なくとも自分のひらめきをスケッチして思いつきを整理するくらいのことは必ず行うだろう。さらに言えば、すべてのデザインは作るための「プラン」を描いてみるところから始まる。これを手元に残し、実際に作られたカタチと比べることはより客観的な立場からの評価につながる。つまりデザインという具体的な行為を考えるなら、まずアイディアと作ることを結ぶ中間ドキュメントを中心に据えて考えるべきと言っても良いと思う。プランはまず自分を気づきに導くための「考える」を支援する装置なのである。
さらにこれを拡張してみると、試行錯誤におけるプランの役割は個人の思考のなかだけに留まらず、自分のアイディアや不明確な構想を他人に伝えるための踏み台として使うことができるし、もっと希望的にとらえれば、他人と一緒に新たなことに気づくためのきっかけともなる。 一般的に、デザイン教育ではカタチを作ることが最も大きな目標となる。これはふつうに考えれば当たり前の話だが、デザイナーとして作り続けることを目指す学生が本当に目を向けるべきは、カタチに至るまでの、そしてそれ以降にも連なる「つながり」である。
デザインにおいて「作る」とは、単にカンやひらめき、思いつきをカタチにして終えることではない。なぜならビジネスとしてのデザインは、作ろうとしているものにリスクを承知でコミットしてくれる多くの人々に支えられているからだ。デザイナーは、何よりもまず社会を前に、なぜこれを作ることが必要なのかを考えるところから始めなければならない。「私は何を、何のためにデザインしようとしているのか」という宣言に続いて、自分にはその役割を遂行できる力があるし、それは余人を持って代え難いと協力者たちに認めてもらわなければならない。
デザインを支えてくれる人々の理解がカタチとなり、社会においてカタチの持つ説得力が評価されたとき、デザイナーはようやくその役割を終えることができる。デザインは、きわめて滞空時間の長い表現なのだ。
デザインの領域が広がるとともに複雑化し、多様な立場の人たちとの協調的作業が必要不可欠となった現代社会では、それぞれに期待される役割とそれぞれが期待する便益を調整する関係づくりが重要になる。異なる立場からクリエイティブな姿勢でモノやコトの実現に挑む人々が、プランを介してうまく目標と方法を共有することができれば、全体を新たなレベルに持ち上げることが可能になる。それぞれの試行錯誤にまたがって各人の意図を伝え、調整する機能を果たすプラン、つまりお互いの意思を媒介する中間ドキュメントの役割は大きい。
表現のために道具が必要なように、自分なりの考えを推し進めるために、また異なる立場の人々と協調してまだ世の中に存在しないものを作り出していくためにも、何らかの協調支援ツールが必要である。優れた表現者は自分なりに、そして優れた組織は彼らなりに「次に進むためのプラン」のたて方を工夫しているし、それを協調的に使う方法を知っている。そして発見を促すデザイン教育の場には、こうした機能を持つ協調支援の道具、互いに気づくための仕組みが求められている。
私は異なる立場の人々を結びつけ、協調的で創造的な関係を作り出すための装置を「場具」と呼んでいるが、ここ何年か、国内外での演習を通じていくつかのプロトタイプの可能性を探ってきた。残念ながら成果のとりまとめまで手が回らないが、これからも新しい技術を積極的に取り入れながら学生たちと一緒に新しい場づくりとそれを支える場具のデザインを考えていきたいと思っている。